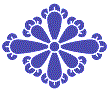
![]()
火取(平安時代の復元品)

古代エジプトで発祥した薫物は2千年の歴史
クレオパトラをも魅了したキフィという薫物(たきもの)は、16種類以上の香材料を用い蜜で練り合わせた、まさに日本の薫物のルーツなのです。キフィは神への聖なる捧げ物であると同時に、人々の心に安らぎをもたらすフレグランスでした。
古代エジプトで発祥した薫物文化は、アラビア半島に伝わり、現在でもアラブ諸国では乳香、没薬(もつやく)、沈香などを合わせるバフールという名の薫物が人々に愛されています。そして、インドに伝わった薫物は仏教と共に中国に伝わり、日本へは奈良時代末に遣唐使が持ち帰った医薬書『千金方』によってその形式が伝わりました。
エジプト、インドにおいて儀式、宗教に用いられていた薫物が、中国に渡って医薬に用いられ、最後に日本に渡って文化、芸術として開花することになるのです。

語られない香道の歴史秘話
明治時代以降の香道では、木片(もくへん)の沈香(じんこう)、白檀のみを焚く木片香道が主流となっています。しかし、18世紀までの江戸時代の香道では、複数の香を混ぜ合わせて蜜などで練り合わせる薫物(たきもの)が隆盛していました。
このことは、江戸時代中期の二人の侍医が著した書が物語っています。まず、公家であり中御門天皇の侍医であった錦小路頼庸(にしきのこうじよりつね。1667~1735)が享保年間に著した薫物書である『香譜記』からうかがい知ることができます。そして、元禄5年(1692)に彦根藩井伊侯の侍医である苗村常伯(なむらじょうはく。1674~1748)が著した『女重宝記』にも薫物の作法、調合方が記されています。
また、江戸時代と言えば徳川家康が『香之覚(こうのおぼえ)』という薫物書を著したことが知られており、そこには家康が愛した「千年菊方」という薫物の方(調合)が示されています。
そして、木片香道の歴史が五百年であるのに対し、薫物香道の歴史は平安時代初期に始まり、千年の長きに亘っていたのです。『源氏物語』の梅枝の帖には最も古い香道の形式である「薫物合わせ」の様子が描かれています。
その後、薫物は茶道の添え物などとしても嗜まれ、今日に至っています。
しかし、このような史実はどこにも書かれず、誰も語ることがなかったのです。

源氏香が平安朝の雅(みやび)?

和風商品のデザインによく見かけられる源氏香の記号
上掲の画像は源氏香の記号が入った茶碗と帛紗ですが、源氏香の記号は和風商品のデザインによく見かけられます。香道をご存じでない方は源氏香の記号が平安時代に作られたと誤解されがちです。
それもそのはずで、源氏香が「平安朝の雅(みやび)」などと、まことしやかに書かれていることが見かけられるのです。しかし、これは『源氏物語』の帖数(全54帖)にヒントを得たゲームの記号で、江戸時代中期に考案されたものなのです。

木片香道と薫物香道の違いとは
さて、近世の木片香道の創始者であり、御家流の祖とされるのが室町時代の公卿、三条西実隆(さんじょうにしさねたか。1455~1537)です。
実隆は当流にとっても重要な人物であり、実隆の著となる家伝の香道書『四辻家薫物書』(文亀年間、1500年頃)に記された薫物の復元製作にも取り組んでいます。
しかし、実隆は後伏見天皇から「ただ色にふけり香にふける中だちとばかりしらむ人」(『後伏見院宸翰薫物方』)と戒められたように、戦国時代で都は窮地にあったにもかかわらず家伝の薫物香道を疎かにし、賭事(かけごと)である「十種香」にふけり、賭事の後は『実隆公記』にも「大酒終夜」と書かれているように、退廃的な婆娑羅(ばさら)の風潮の渦中の人だったのです。
残念ながら実隆は家伝である薫物香道を疎かにして香を合わせることなく、沈香の木片だけを使い邪道である賭事に興じていたのですが、この賭事の形式である「十種香」が木片香道における「組香」というゲーム形式の始まりなのです。
このように、木片香道が非日常的ゲームであるのに対し、薫物香道は日常的嗜(たしな)みであることが、大きな違いと言えます。

千年の歴史がある貴重な日本文化
実隆の家伝である薫物香道は、言うまでもなく実隆の時代に始まったものではなく、平安時代に隆盛した形式です。
平安朝薫物は秘法などを用い、沈香を主体として最小4種、最大12種の香の粉末などを、蜜または甘葛(あまづら)で練り合わせて作り、その優雅で深遠、そして複雑で変化に富む薫りを楽しむものでした。
その代表的なものに六種(むくさ)の薫物と呼ばれる黒方、梅花、荷葉(かよう)、侍従、菊花(きっか)、落葉(らくよう)という6種類の空薫物(そらだきもの、すなわち空間に解き放つための薫物)がありました。
薫物の奏香は嗜みとしてだけでなく、『源氏物語』の梅枝の帖に書かれているように、最も古い香道の形式である「薫物合わせ」という行事があり、判者(はんじゃ、判定者)が判詞(はんし、判定の言葉)を述べるなどの作法が確立されていました。
前述のように、木片香道は室町時代の16世紀に始まり今日までの五百年であるのに対し、薫物香道の歴史は平安時代初頭の8世紀に始まり18世紀までの「千年の歴史」があるのです。

最古の薫物指南書・勅撰『薫集類抄』
土御門天皇の曽祖父で、紫式部の血胤(来孫)である平安末期随一の知識人、それが藤原範兼(ふじわらののりかね、嘉承2年~長寛3年1107~65、通称岡崎三位。)です。歌人、歌学者として知られていますが、二條天皇に元号考案を命ぜられただけでなく、長寛年間(1163~65)に『薫集類抄』の撰修を命ぜられました。
この勅撰『薫集類抄』は、わが国に現存する最古の薫物指南書であり、当流の宝鑑(手本となる書物)と位置づけています。
薫物に関する書物は多い中で、前述の実隆の家伝書『四辻家薫物書』のような私撰書とは異なり、公的な勅撰書として纏められた『薫集類抄』は、その格式だけでなく信憑性、歴史性という観点からも極めて貴重な書物なのです。
(注)『日本書紀』が勅撰史書であるように、「勅撰」には「勅命により編纂された書物」の意があります。
勅撰『薫集類抄』は、「諸方」の帖から始まり、27種、107方もの貴重な調合法が収載されています。そして、26人の合香家の名は時系列に並べられており、同じ名の薫物でも合香家によってその香りは驚くほど異なり、この時代の美意識と感性の豊かさを感じます。
同書には、この他に飲む、塗る、入浴に用いるなどの合香の方(調合)が示されています。
また、和合(ブレンド)した薫物は、埋み(うずみ)という熟成を行います。薫物の天敵は黴(かび)ですので低温熟成が基本です。(当流では特別の方法を代用して簡単に熟成させます。)ところが、加熱し発酵させる指示がある方もあるのです。「控えめであり秘することが雅(みやび)」とされた平安時代の美意識によって書かれた文献を読み解くのは難しくもあり、また楽しくもあります。

閑院流香道とは
日本の香道の祖と位置づけられるのが、閑院大臣・藤原冬嗣(ふじわらのふゆつぐ)です。前述のように「六種の薫物」という6種の平安朝空薫物の内の3種である「梅花」「侍従」「黒方」の最古にして原型の調合方を考案したのが冬嗣であり、薫物の最古の調合者が冬嗣なのです。
冬嗣は、奈良時代の宝亀6年(775)に生まれ、平安時代初期に嵯峨天皇、淳和天皇に重用され、詩人、歌人、武人、政治家、そして薫物(たきもの)香道家という、比類ない該博多能な人物であり、多大な功績を遺した偉人です。
当流の牌標は、まさしく冬嗣の称号である閑院大臣に肖り掲げています。閑院とは、左京三条二坊にあった冬嗣の自邸のことです。
さて、勅撰『薫集類抄』における六種の薫物に用いられる香材料は11種のみですが、その内の1つが麝香です。
これまで、麝香は絶滅危惧種である麝香鹿の雄を殺して、香嚢(ジャコウを分泌する腺)を採取していましたが、現在では飼育個体から掻き出す方法がとられています。しかし、この採取プロセスにおける動物への負担やストレスが倫理的な問題は解決されていません。
当流では、動物愛護の観点から、勅撰『薫集類抄』に掲載されている107の調合方の中から、麝香を用いない33種の調合方の他、平忠盛原著『香之書』他、同様に麝香を用いない調合方で薫物作りを行っています。これが、当流の最大の特色であり、また六種の薫物だけでなく、季節、催事に寄せて創作する作物(つくりもの)を重んじています。